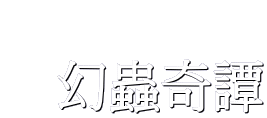|
蚤の章…2
「合格。でも、その靴は頂けないわね。折角靴を履くっていう文化を持っているんだから、手入れぐらいしなさいな」
ミツは夏雄の行儀に関して煩い。
踵を踏んで来なかったのは正解だったが、お小言はくらった。
「次は洗ってくるよ」
「帰ったら、洗いなさい」
美しい顔がスッとなると結構怖い。
「はい、洗います」
実際洗うかどうかは別としてこの場での正解を口にした。
「よろしい。ふふ、おはぎね…さすが、リンさんだわ」
ミツの顔が緩む。
リンとは夏雄の祖母の名前だ。漢字では凛と書く。
「繁さんの相手してて。これ、皿に分けてくるから。夏雄ちゃんも食べていくでしょ?」
繁は夏雄の祖父の繁雄のことだ。
「うん。食べる。ミツさんのは、黄な粉だから」
「承知しています」
祖母から何かしてもらうことにミツが喜ぶ傾向にあることには、夏雄も気付いていた。
自分の前を歩くミツの後ろ姿からも、ミツの機嫌の良さが読み取れた。
そして、久しぶりに夏雄は『その瞬間』を目にした。
「うわ、ミツさん! 出てきた!」
ミツが歩を止め、慌てて自分の頭を触った。
「違うよ、そっちじゃない」
夏雄の言葉を受け、頭を触っていた手をミツは臀部に移動させた。
「失礼。嬉しいとね、ついつい」
着物の生地を通り越し臀部からぶら下がった白いフサフサしたものをミツが触る。
「尻尾、僕は構わないけど」
「駄目ダメ。このところ年のせいか、ちょっと気が緩むとこれだから」
ヤダヤダ、と言いながらミツがまた歩を進める。
ミツの尻尾はシュルシュルと縮んでいき、尻尾は見事に消えた。
じいちゃんいいよな…と夏雄はミツの尻尾を見る度に思う。
ミツが尻尾を見せる相手は自分の祖父だけだ。
触ったこともない。
一度触ってみたい…と前々から思っていた。
しかし、子どもには駄目だと言われ、まだ一度も触れたことはない。
いつか、触らせてもらう日がくるのかな?とその日が来るのを、夏雄は心待ちにしている。
「夏雄、よう来たな」
古い畳の匂いのする居間に、夏雄の祖父が座っていた。
孫の登場に、目尻の皺を深くしながら、笑顔を向けた。
「うん。ばあちゃんに頼まれた。おはぎ持って来たよ」
「お、そりゃ、楽しみだ。ばあさんの作るおはぎは絶品だ」
「知ってるよ。じいちゃん、寝てた? 涎の跡あるよ」
白髪で猫背の祖父が、怠そうに顎の下を手の甲で拭う。
「そこじゃないよ、頬に向かって横向き。ミツさんに膝枕してもらってた?」
ちゃぶ台の上に、ミツ愛用の木彫りの手鏡があったので、それを祖父に渡した。
「バレタか。耳ん中、ホジホジしてもらってたら、気持ちよくなってな。いつの間にか寝てたらしい」
「ミツさんの着物、汚したんじゃない?」
「ワシは夏雄と違って、ミツから叱られたりせんぞ」
「なんだよ、それ。僕も叱られないし……注意はされるけど」
途中から小声になった夏雄を、祖父の繁雄が「ははは」と愉快そうに笑った。
「来た早々、『注意』されたんか? そんな顔しとるぞ」
「バレタか」
祖父の真似をして答えた。
「お前はミツに愛されてるからのう。高雄は叱られたことなかったはずだが。ハハハ」
夏雄の父親が高雄だ。男三代、『雄』の字が名前に入る。
狙ったのではなく、偶然らしい。
だが、ミツの話によると、その前、夏雄の曾祖父の名が虎雄だったらしいので、偶然にしちゃあ、出来すぎた話である。
「そうなんだ。でも、父さん、ミツさん苦手だよね。会うと緊張してない?」
高雄がミツと目を合わそうとしないことは、幼い頃から気付いていた。
極力会うのを避けていることも知っている。
「そりゃ、緊張するだろ。ミツは高雄の初恋の相手だからな」
「えー、それ本当の話? 初めて聞いた…」
銀行の支店長をしている堅物の父親に初恋があったことだけでも驚きだったが、その相手がミツとあっては尚更だ。
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|